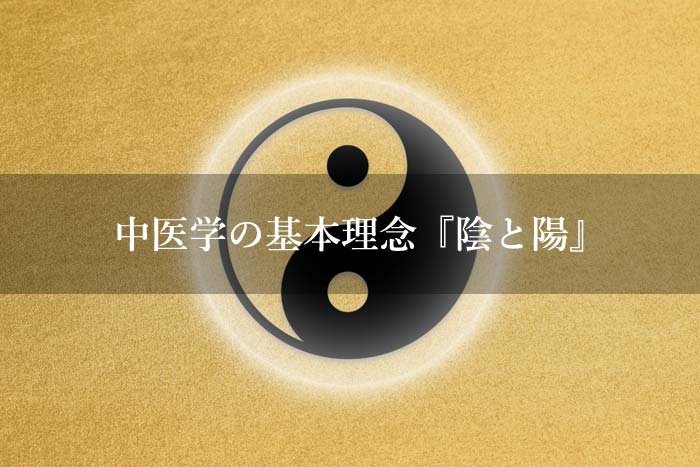
対立する性格の「陰」と「陽」
陽気(明るい)・陰気(暗い)など、陽と陰の文字は、身近に使われていますね。
中国の古代哲学思想でも「物事はすべて陰と陽の対立する性格の2種に分けることができる」という概念があり、中国漢方の中医学においても、基本の理念となっています。
すべての事物は、促進と拮抗という対立が存在しつつ統一されていると考えるのです
陽に分類されるのは
自然界では、天や昼、熱、明るい、上昇、運動などが陽に属します。人の体においては、体の表面や背中の部分、体の上部、六腑、気(機能)、興奮や亢進した状態、活動などが陽に属します。
陰に分類されるのは
自然界では、地や夜、寒、暗い、下降、内向、・静止などが陰に属します。人の体においては、体の裏面や腹部、体の下部、五臓、血(血液)、抑制や衰退の状態、静止などが陰に属します。
陽の過不足でおきやすい症状
陽は体を温めたり、消化吸収・排泄をしたり、体を動かす原動力なので、不足すると、冷えて低体温、元気が出ない、食欲不振、無気力、疲れやすいなどの症状がでます。
一方で過剰になると、興奮してイライラすることもあります。皮膚に赤みやかゆみを伴う炎症がおきることもあります。
陰が不足した状態で、相対的に陽が過剰になると、夜間微熱が出たり、のぼせやほてり、めまいが起きることもあります。
陰の過不足で起きやすい症状
陰は体を潤し粘膜や内臓の働きを正常に保つ作用があるので、陰が不足すると、のどの乾燥、肌の乾燥、ドライアイ、ドライマウス、筋肉のつりなどがおきやすくなります。不足が極まると熱が生じ、のぼせ、ほてりなどがおきることがあります。
また陰に属する血が不足すると、肌の乾燥、髪や爪が弱くなり、冷えやすくなります。血の不足は、落ち込み・憂鬱・焦燥・不眠など精神的な不調にもつながると考えます。婦人科機能にも血は必要なので、不足すると、生理不順、生理痛、無月経などをひきおこすこともあります。
陰の過剰は、余分な水がたまるため、むくみや体の重だるさ・頭重感などにつながります。梅雨のように湿度の高い時には、陰の過剰による重だるさ・むくみ・頭痛・関節の重だるさなどがひどくなる傾向があります。
「気」「陰」「血」
また、中医学では、「気」や「陰」「血」という表現を使いますが、「気」は、直接目には見えない、機能的な作用で、陽に属します。
気は、呼吸をする、体を動かす、血液を流す、食べ物を食べ、消化吸収したり排泄する、体を病気や感染症から守る、体温を保つなど、すべての生理機能に関わっています。
一方、「陰」(体液)「血」(血液)は物質的なもので、陰に属します。これらは、お互い増えたり減ったりしながら、相対的平衡を保つのが正常とされます。
「五臓」と陰陽
中医学では、「肝」「心」「脾」「肺」「腎」の五臓の状態を把握し処方の参考にしますが、五臓の中にも、陰陽があります。
たとえば、免疫や各種ホルモン分泌・骨や髪の成長・腎機能・男性機能・婦人機能に関わる「腎」においても、腎陽・腎陰があり、その偏りで体調が変わります。
腎陽不足に偏ると、顔色が青白い、下半身の冷えや痛み、生理痛、寒がり、寒さで悪化する気管支喘息や咳、頻尿、むくみ、食欲不振、疲れやすいなどが起きやすくなります。腎陰不足に偏ると、肌が乾燥してかゆくなる、目がしょぼしょぼしたりドライアイ、口が渇く、夕方ほてりやのぼせがひどくなる、寝汗、不眠などがおきやすくなります。
「肺」は陰の不足が起きやすく、のどの乾燥、ドライマウス、空咳などは日常的に起きやすい症状です。「肝」は陽が過剰になりやすく、イライラ、精神的な興奮、顔の紅潮などがよくおきます。
陰陽はバランスが大事
陰と陽は、どちらがよいとういうわけではなく、お互いに助けあい、また生み出しています。大事なのは、陰と陽がバランスよく体内で存在し、機能することです。
陰陽の過不足は、日常生活において身近に起きやすく、また必ずサインを出します。体調以外にも、舌の状態でいうと、陽(熱)過剰であれば赤くなり乾燥しやすくなります。
陰の過剰であれば、白っぽく苔もつきやすくぽてっとした感じになります。
陰の不足であれば、舌に列紋が生じることもあります。
陰陽の失調は、長引くとさらなる不調や病気につながります。未病のうちに対策を考え、バランスがとれるよう心がければ、大きな不調につながらずすむかもしれません。
気になることがあれば早めにご相談くださいね。
